先日、「データと論文の間―フィールドサイエンスにおける論証とは」というワークショップで話をしました。イベントの詳細は<こちら>です。
話は、「データと理論:データあっての理論か、理論あってのデータか」というタイトルで、我々が扱う「データ」について考えてみたものです。特にアッと驚くようなことは何も言っていませんが、日々の研究の中ではついつい忘れがちであるポイントについて注意を促すような趣旨のものです。
言葉遣いと人となりの結びつきがステレオタイプ化した「役割語」現象についてはこれ:
言葉遣いのキャラ化とその活用の現象を「方言コスプレ」として論じたのがこれ:
田中ゆかり『「方言コスプレ」の時代――ニセ関西弁から龍馬語まで』岩波書店
どちらも我々の言葉遣い選びが「人となり」をどう形作っているかを良く見せてくれます。
今週香港大学の学生さんたちにむけたワークショップをやっています。毎日忙しいですが、いろいろな意味で感慨深い日々です。
訪問しているのは言語学を専攻している学部生25人ほどのグループ。香港大の言語学科では、海外研修旅行を核とした実習コースが必修だそうで、今回の東京への訪問はそのコースの一環とのことです。内容としては、消滅しかかった言語を中心とした研究が未開発の言語を調査し記録する研究(言語ドキュメンテーション研究)の意義とその方法について、講義とプロジェクト実習を織り交ぜて学んでもらう4日間のプログラムです。
香港大学では今言語ドキュメンテーション研究を強化しようとしているのですが、我々がかれこれ8年ほどこの言語ドキュメンテーション研究のワークショップや共同研究活動の実績を積み上げてきたことを評価してくれて、今年の海外研修の訪問先の一つとして我々の研究所を選んでくれました。
8年前に言語ドキュメンテーション研究の共同研究を軸としたプロジェクトを始めたときは、海外の先進的拠点の研究者から懸命に学ぶことばかりでした。それが、最近では毎年開催しているワークショップに国外からの受講希望者が集まるようになり、海外でのワークショップの講師として声がかかったりするようになってきました。そして、今回、あちらからワークショップを提供してくれと依頼がきたんです。自分たちは教えてもらう立場だとずっと思っていたので、たとえできばえはまだまだであったにしても、来てもらった人たちに喜んでもらえているワークショップを提供できていることに、なんか不思議な感慨を感じています。
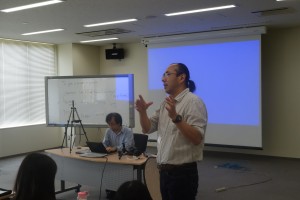
(photo by: Asako Shiohara)
あともうひとつ。これまで、留学や海外研修に学生や子どもを送り出したり、見送ったりすることは多かったけれども、自分がホストファミリー以外の形で来日する海外学生の学びに直接関わったことは少なかったので、今回のように海外研修経験の大きな部分を提供してあげることに、大きな責任と漠然とした喜びのようなものを感じています。ちょうど同じくらいの歳の娘を持っていることもあり、子どもたちを送り出す親御さんが持っているであろう心配が入り交じりながらも子どもが持ち帰る経験と土産話を楽しみにしている気持ちを考えると、少しでも良い経験を持って帰らせてあげたいと思えてきます。
と、まあ、準備しているときには深く考えもしませんでしたが、いろいろ感じ入っている今週です。
動物が人間の言語を習得するのは難しいとされていますが、これまでに行われてきた動物に言語を教える試みのいくつかを紹介します。
なんか最近、上から命令調の本のタイトルが多いですね。しかも、内容も小泉首相以来の一言言い切り型。今日見たのは
「長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい」
なんでこんなタイトルが流行るんでしょうね。
東外大AA研の共同研究プロジェクト「複雑系としての言語」の活動の一環として開催しました。
今回のワークショップは、文法の中での ‘tight’(固定的、構造化の度合いが高い)と ‘loose’(流動的、構造化の度合いが低い)というテーマでの企画でした。
文法体系は、言語パターンが言語使用の中で固定化、構造化されて形成され、変化していくものだと考えた時、その固定化・構造化が言語のどの部分でどのように進むのかを捉えることは文法の特性を理解する上で重要です。そこで、特に会話を中心とした自然談話におけるパターンの固定化・構造化の性質や分布についての報告を集め、議論しました。
発表要旨、ディスカッションでのメモなどはこちらのワークショップページでご覧いただけます:
『文法とコミュニケーションの怪しい体系性―ありのままの言語研究の挑戦』
※講演スライドはこちら
【要旨】
人間の社会的な営みと結びついている現象は、マクロレベルで見えるシステム性・一般的規則性とミクロレベルで見える多様性・複雑性の両面を併せ持っているおもしろみがある。しかし、この二つの側面は、しばしば切り分けられ、前者のシステム性こそが理論的研究の中心的対象であると考えられる。言語研究もその例外ではない。今の言語研究では、マクロレベルで見える一元性(一般規則、普遍性)こそが言語現象とそこに見られる体系性の本質だと考えられてきた。
ところが、人々が言語を使う現場に目を向けてみると、そこには言葉遣いのバラツキやユレ、文脈依存の規則性、複数のパターン間の不整合、形式や用法の不断の変化など、一元的体系という理論的理想とは相容れない「不都合な現実」が多く観察される。これまで、そうした事実はあくまで言語運用上の表面的な問題であって、言語システムの本質に関わる問題ではないと切り捨てられがちであった。
都合の悪い現実から切り離すことでシステムの内的整合性を保とうというのは効率的な解決法にも見えるが、それでは、言語使用の現場に見られる多くの事実を言語研究の外に押しやり、結果として言語研究が人間の社会活動を理解する上で果たしうる役割を狭めることになる。さらに、ミクロレベルでの多様性・雑然性とマクロレベルでのシステム性を併せ持つ現象は、経済などの他の社会現象のみならず自然界でも多く観察されている。とすれば、システム性と多様性という一見矛盾する性質が共に本質を成すものとして言語システムを捉えることは理にかなっているように思われる。
現在東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所で進められている基幹研究の一つ「言語ダイナミクス科学」はまさにそうした認識が出発点となっている。人々が日常生活の中で意味を伝え合う。その生きた活動の中での言語の使われ方、言語表現の組み立て方を見ると、言語体系を作っている規則性やパターンは明らかに多様性と変化を内包した動的なものであることがわかる。その動的な体系性をつきとめる営みは、現代の言語研究で広く前提とされる、言語を静的な整合性・規則性の体系として捉える「共時言語学」の理論的・概念的枠組みの多くを組み替えることにまで挑戦を広げるものである。
Mukherjee, Animesh, Vittorio Loreto, and Francesca Tria. 2012. ‘Why are basic color names “basic”?’ Advances in Complex Systems 15 (03n04): 115001 (13 pages).
{2014-04-24: 院ゼミ}
【論文のめざすところ】
’Basic Color Terms’の研究 (Berlin & Kay 1969)において明らかにされた色彩語彙に見られる「basicness」の階層を統計的に再検証し、「basicness」を統計的に性格づけることができるか探る。
言語学における’Basic Color Terms’の研究では、「basicness」を語彙の内部構造、意味範囲、使用範囲など主として言語構造上の基準によって性格づけていた。この研究では、「basicness」により実証的な性格付けを試みる。
【感想】
・論文として読みにくい:前提となっている議論や先行研究の内容について、論文の論理の流れを追うのに必要であるにもかかわらず、十分に説明されていないため、論について行きにくいところが多々ある。
・筆者たちはどうも言語や言語学に関する理解が不十分であるように思われる。どうやらこの論文で行おうとしているのは、’Basic Color Terms’の研究ではなく、「basicness」という概念を統計的に分析すると言うことだけに関心があるように見受けられる。